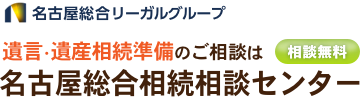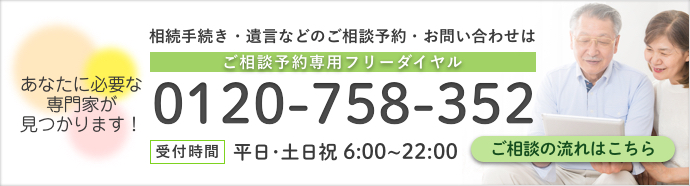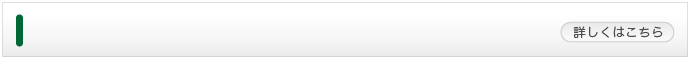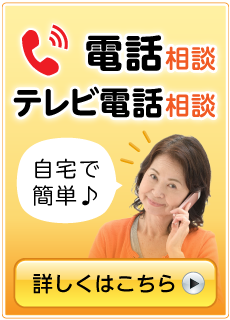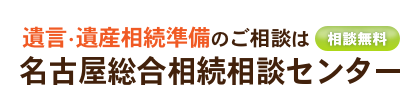相続人の中に認知症の方がいる

社会の高齢化に伴い相続手続きにおいて、相続人の中に認知症の方がいるケースも出てきます。今回は、そのような場合に、どのように相続手続きを行うかをお話ししたいと思います。
とりうる方法
通常の相続手続きは、相続人の間で相続財産のうち何を誰が相続するかを話し合い、相続人全員の合意の下で財産の分け方を決定します。これを遺産分割協議といいますが、相続人の中に高齢による認知症や知的障害等により、十分な判断能力がない方がいる場合、この遺産分割協議ができなくなります。
もし認知症や知的障害をもつ相続人を無視し、その方を除外して遺産分割協議を行ったとしても、それは無効となります。
このような場合には、「成年後見制度」を利用することになります。家庭裁判所に成年後見人選任申立を行い、本人に代わり財産管理をする成年後見人を立て、その者と他の相続人とで遺産分割協議をします。
『成年後見制度』の注意点
しかし、成年後見人には、一般的に親族がなることが多く、相続の遺産分割の場合には、被後見人と成年後見人とが共に相続人となり、お互いの利害が対立してしまう利益相反の関係になってしまいます。このままでは、遺産分割協議を行えないので、さらに家庭裁判所にて「特別代理人」の選任手続きをする必要もあり、手間や時間もかかります。
また、一度、成年後見制度を利用し、成年後見人が選任されると、遺産分割協議が終了しても、成年後見人の仕事は終わりません。被後見人が財産管理をしてくれる代理人を必要としている状況は変わらないので、被後見人の意思能力が回復したり被相続人が亡くなるまでは成年後見人の仕事は継続することになります。
弁護士相談のススメ
以上のように、相続人の中に認知症の方がいる場合、相続手続きがとても煩雑になります。お困りのかたは、弁護士に一度ご相談ください。
遺言作成もご検討下さい。
また、家族に認知症・知的障害等の方がいる場合には、遺言を作成しておくことをお勧めします。遺言があれば、相続人全員で遺産分割協議をすることなく遺言に従って相続手続きをすることができるからです。
ただし、遺言の作成にも法定の様式があり、その様式をみたさない遺言は有効とならないので、遺言作成をご検討の際にも弁護士にご相談いただければと思います。
-
最新の記事
- 被相続人の借金を返済してしまったが、相続放棄できる?医療費は?
- 【生前贈与の選び方】暦年贈与と相続時精算課税の違い
- 生前対策として贈与を考えています。具体的な方法を教えてください
- 高齢者の身元保証サービスとは?
- 次世代経営者へのバトンタッチ
~自社株(非上場株式)等の相続税・贈与税の納税猶予の特例~ - 高齢者の生活と資産を守るための「家族信託」の活用事例
- 認知症の人の所有住宅 221万戸
- 終活と遺言
- 生命保険金の非課税枠
- 生前贈与~子や孫へ財産を引き継がせる方法
- 遺言信託とその公示
- 遺留分制度の改正により、遺留分及び遺留分侵害額の算定方法が明文化
- 配偶者居住権を活用した節税メリットとリスク
- おしどり夫婦贈与(贈与税の配偶者控除)
- 住宅取得資金等の非課税の特例
- 秘密証書遺言書
- 配偶者なき後問題
- 10年以上取引がない預金はどうなるのでしょうか?
- 相続財産になる前に、不動産の所有権を放棄できるのか
- 法務局における遺言書の保管等に関する法律について
-
月別
- 2025年12月 (1)
- 2025年10月 (1)
- 2025年8月 (1)
- 2025年5月 (1)
- 2024年4月 (1)
- 2022年9月 (1)
- 2021年9月 (2)
- 2020年9月 (1)
- 2020年6月 (1)
- 2020年3月 (1)
- 2020年1月 (1)
- 2019年12月 (1)
- 2019年7月 (2)
- 2019年5月 (2)
- 2018年12月 (1)
- 2018年11月 (1)
- 2018年9月 (1)
- 2018年8月 (1)
- 2018年7月 (1)
- 2018年6月 (1)
- 2018年5月 (2)
- 2018年4月 (1)
- 2018年1月 (1)
- 2017年10月 (1)
- 2017年8月 (1)
- 2017年7月 (2)
- 2016年9月 (3)
- 2016年5月 (1)
- 2016年3月 (1)
- 2016年2月 (1)
- 2016年1月 (1)
- 2015年10月 (1)
- 2015年9月 (1)
- 2015年7月 (1)