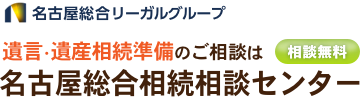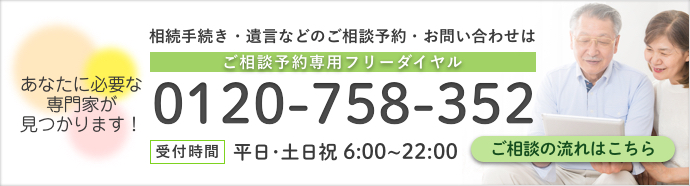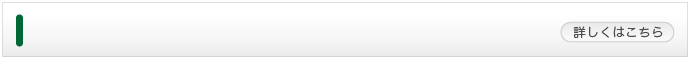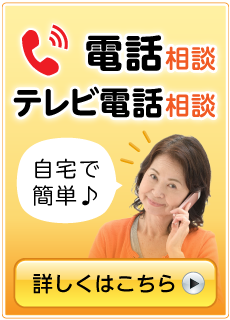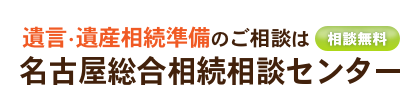認知症の人の所有住宅 221万戸
はじめに

9月16日付けの中日新聞に、「認知症の人が所有する住宅が2021年現在、全国に221万戸あるとの推計を第一生命経済研究所がまとめた。」との記事が掲載されました。
「約30戸に1戸に当たる計算で、40年には280万戸に増える見通し。」ともあります。
認知症の方のご自宅であった不動産が、介護施設への入居により空家になることもあります。
空家の管理が適切になされていればよいですが、放置したままですと近隣とのトラブルになる恐れもあります。
また、売却したい場合でも、ご本人の判断能力に衰えがある状況ではスムーズに売却ができず、成年後見制度を利用しなければいけないケースもでてきます。
その場合でも元自宅不動産の売却においては家庭裁判所の許可が必要となる事もあり、手間や時間がかかってしまいます。後見制度は一度スタートすると、本人の判断能力の回復がない限り途中でやめることができません。
「不動産の売却手続きが終了したから、もう後見人は必要ないよ」という訳にはいかず、後見人報酬の負担が、ご本人が亡くなるまで続きます。
そういったこともあり、なかなか成年後見制度の利用が進んでいない現状があります。
事前に対策をしておくことで、成年後見制度を利用せずとも、認知症の方の不動産管理をする方法があります。
「家族信託」です。
家族信託のすすめ

ご本人の判断能力がしっかりしているうちに、「家族信託」により信頼できるご家族に財産管理を任せておくのです。
そうすることで、ご本人が認知症になったとしても適切な時期にご家族の方が空家の管理や自宅不動産の売却手続きを進めることができます。
9月14日には、厚生労働省から、「全国の100歳以上の高齢者が過去最多の86510人になった」との発表もありました。
人生100年時代ともいわれ、高齢化の一途をたどっています。亡くなるときまで元気でいられるのが理想ですが、誰しも認知症になる恐れがあります。
健康寿命は、2016年の数値では男性72.14歳、女性74.79歳となっており、平均寿命との差である延命期間(日常生活に制限のある生活を送る期間)が10年程度あることになります。
何も対策をとらず、この延命期間にはいってしまうと、資産が凍結されたりして、ご本人の財産管理についてご本人だけでなくご家族も困ってしまう事になります。
そうならないために、早めに対策をとっておくことが大事です。
「家族信託」についてお悩み・ご相談は専門家まで。
-
最新の記事
- 熟年離婚後、元配偶者への遺言はどうなる?
- 被相続人の借金を返済してしまったが、相続放棄できる?医療費は?
- 【生前贈与の選び方】暦年贈与と相続時精算課税の違い
- 生前対策として贈与を考えています。具体的な方法を教えてください
- 高齢者の身元保証サービスとは?
- 次世代経営者へのバトンタッチ
~自社株(非上場株式)等の相続税・贈与税の納税猶予の特例~ - 高齢者の生活と資産を守るための「家族信託」の活用事例
- 認知症の人の所有住宅 221万戸
- 終活と遺言
- 生命保険金の非課税枠
- 生前贈与~子や孫へ財産を引き継がせる方法
- 遺言信託とその公示
- 遺留分制度の改正により、遺留分及び遺留分侵害額の算定方法が明文化
- 配偶者居住権を活用した節税メリットとリスク
- おしどり夫婦贈与(贈与税の配偶者控除)
- 住宅取得資金等の非課税の特例
- 秘密証書遺言書
- 配偶者なき後問題
- 10年以上取引がない預金はどうなるのでしょうか?
- 相続財産になる前に、不動産の所有権を放棄できるのか
-
月別
- 2025年12月 (2)
- 2025年10月 (1)
- 2025年8月 (1)
- 2025年5月 (1)
- 2024年4月 (1)
- 2022年9月 (1)
- 2021年9月 (2)
- 2020年9月 (1)
- 2020年6月 (1)
- 2020年3月 (1)
- 2020年1月 (1)
- 2019年12月 (1)
- 2019年7月 (2)
- 2019年5月 (2)
- 2018年12月 (1)
- 2018年11月 (1)
- 2018年9月 (1)
- 2018年8月 (1)
- 2018年7月 (1)
- 2018年6月 (1)
- 2018年5月 (2)
- 2018年4月 (1)
- 2018年1月 (1)
- 2017年10月 (1)
- 2017年8月 (1)
- 2017年7月 (2)
- 2016年9月 (3)
- 2016年5月 (1)
- 2016年3月 (1)
- 2016年2月 (1)
- 2016年1月 (1)
- 2015年10月 (1)
- 2015年9月 (1)
- 2015年7月 (1)