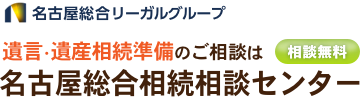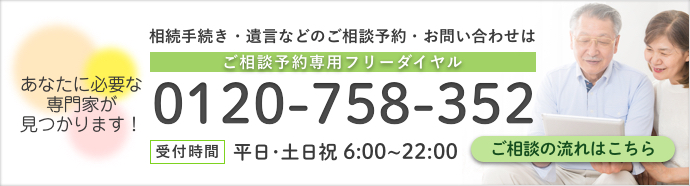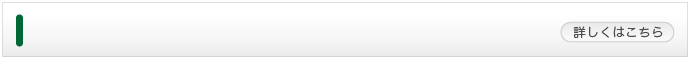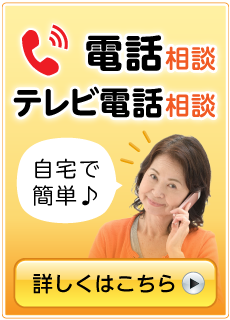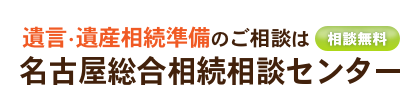相続開始を知ってから3ヶ月を経過してしまったら
公開日:2016年6月17日 / 更新日:2025年4月16日
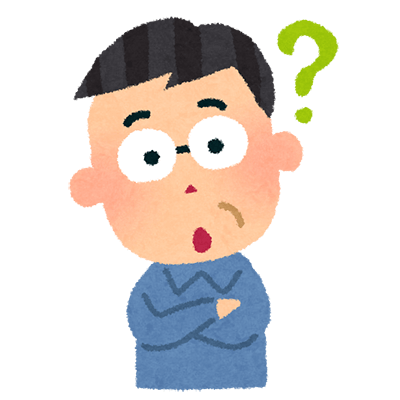
相続人が、相続放棄又は限定承認をするには、家庭裁判所にその旨の申述をしなければなりません。申述は、民法により自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内にしなければならないと定められています。申述先は、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所です。
相続の開始を知ってから3ヶ月以内に相続放棄又は限定承認をしないと、その相続人は、単純承認したものとみなされます。
しかし、相続するかしないかという判断は容易にできない場合もあるでしょう。相続財産を慎重に調査したうえで相続放棄するか否かを決めたいと考えるのが通常です。
また、思いもかけない相続により自分が相続人になることもあるでしょう。
これまでまったくつきあいのなかった親族が亡くなったが、実は自分が代襲相続人だとわかった…
第一順位の相続人が全員相続放棄をして、第二順位である自分が相続人になった…
いつ、どんな場合にも3ヶ月経過してしまったら相続放棄できない、となってしまうと、あまりに相続人に酷な結果になりかねません。
(1) 熟慮期間伸長の手続き
相続人が、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に相続財産の状況を調査してもなお、相続を承認するか放棄するかを判断する資料が得られない場合には、相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立てにより、家庭裁判所はその期間を伸ばすことができます。
(2) 3ヶ月経過後の相続放棄が認められる場合
3ヶ月の熟慮期間がはじまるのは、「自己のために相続の開始があったことを知った時」と定められています。「被相続人が死亡した事実を知り」かつ「自分が相続人となったことを知った時」から3ヶ月の熟慮期間が始まるのです。
つまり、被相続人が亡くなってから3ヶ月以上が経っていても、「被相続人の死亡の事実を知ったときから3ヶ月以内」であれば相続放棄できることになります。
また、先順位の相続人がいるので自分は相続人でないと考えていたところ、その先順位者が相続放棄をしたことにより自分が相続人となったような場合で、被相続人が死亡したことは知っていたが、先順位の相続人が相続放棄をしたとの事実を知らされていなかったような場合には、「自分が相続人となったことを知った時」つまり、先順位者が相続放棄した事実を知ってから3ヶ月以内であれば相続放棄できることになります。
(3) 特別な事情がある場合の熟慮期間の起算点
特別な事情がある場合、例外的に熟慮期間の起算点が後に繰り延べられることがあります。
最高裁判決昭和59年4月27日は、「相続人が、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に相続放棄をしなかったのが、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて、その相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人において上記のように信じたことについて相当な理由があると認められるときには、相続放棄の熟慮期間は相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識した時、または通常これを認識しうるべき時から起算すべきものである。」としています。
3ヶ月経過後の相続放棄が認められるか否かは、裁判所が個別の事情を様々に考慮して決定します。3ヶ月経過後の相続放棄申述をする際には、専門家に相談して手続きを進めることをお勧め致します。