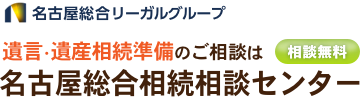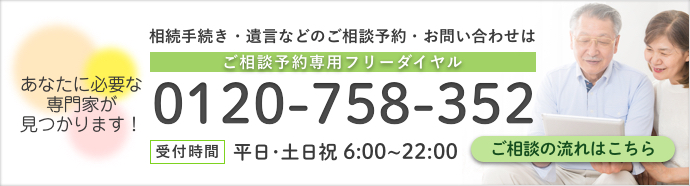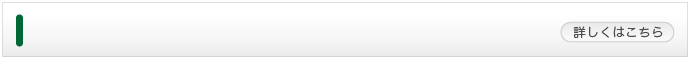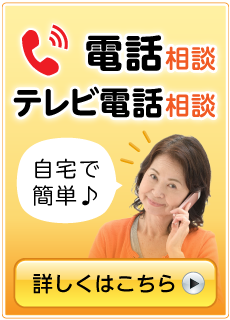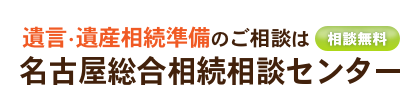【生前贈与の選び方】暦年贈与と相続時精算課税の違い

ご質問:両親ともに相続税がかかる場合
相続税の生前贈与を考えています。2つの贈与の方法(暦年贈与と相続時精算課税)のどちらが良いでしょうか?
前提
- 父の財産:不動産5,000万円/金融資産7,000万円/生命保険1,000万円
- 母の財産:金融資産5,000万円
- 父の年齢:80歳 母の年齢:75歳
- 子:2人 孫:4人
アドバイス
父からの贈与:
子 → 相続時精算課税
孫 → 暦年贈与
母からの贈与:
子 → 暦年贈与を選択し、何年か後に相続時精算課税を選択
孫 → 暦年贈与
毎年の非課税金額
もらった人について1年あたり110万円の非課税枠がありますが、相続時精算課税は贈与者を選択できます。
つまり、父からの贈与を「相続時精算課税」、母からの贈与を「暦年贈与」とした場合、年間で220万円の非課税枠があることになります。
相続が発生した場合
暦年贈与は相続が発生した場合、過去7年分(令和13年以降)の贈与財産は全額相続財産に加算されてしまいます。
しかし、相続時精算課税を選択している場合、令和6年以降の贈与財産は年間110万円までは相続財産に加算されません。
例えば、毎年110万円×7年=770万円の贈与をしたとします。
| 区分 | 非課税額 | 相続財産加算額 |
|---|---|---|
| 暦年贈与 | 100万円 | 660万円 |
| 相続時精算課税 | 770万円 | 0万円 |
相続時精算課税の選択方法
何もしないと「暦年贈与」となります。「相続時精算課税」を選択するためには、「相続時精算課税選択届出書」を税務署に提出します。
いったん選択すると取り消しはできません。
暦年贈与から相続時精算課税への切り替えのタイミング
贈与は「認知症」になるとできなくなります。
そのため、贈与者の健康状態を考慮して「相続時精算課税選択届出書」を提出するようにしましょう。
孫に対する贈与
孫に対する贈与は、相続財産への加算はありません。
また、孫が未成年の場合は親権者(両親)が贈与に関する法的行為を行います。つまり、通帳も親が管理することになります。
ただし、成人(18歳)になった後は孫自身が管理する必要がありますので、注意しましょう。
まとめ
生前贈与は有効な手段となりますが、贈与税を支払ってでも贈与した方が有利になるケースや、やり方によっては贈与自体が否認され、名義預金として相続財産に加算されることもあります。
生前贈与をお考えの場合には、税理士等の専門家に相談されることをお勧めいたします。
-
最新の記事
- 熟年離婚後、元配偶者への遺言はどうなる?
- 被相続人の借金を返済してしまったが、相続放棄できる?医療費は?
- 【生前贈与の選び方】暦年贈与と相続時精算課税の違い
- 生前対策として贈与を考えています。具体的な方法を教えてください
- 高齢者の身元保証サービスとは?
- 次世代経営者へのバトンタッチ
~自社株(非上場株式)等の相続税・贈与税の納税猶予の特例~ - 高齢者の生活と資産を守るための「家族信託」の活用事例
- 認知症の人の所有住宅 221万戸
- 終活と遺言
- 生命保険金の非課税枠
- 生前贈与~子や孫へ財産を引き継がせる方法
- 遺言信託とその公示
- 遺留分制度の改正により、遺留分及び遺留分侵害額の算定方法が明文化
- 配偶者居住権を活用した節税メリットとリスク
- おしどり夫婦贈与(贈与税の配偶者控除)
- 住宅取得資金等の非課税の特例
- 秘密証書遺言書
- 配偶者なき後問題
- 10年以上取引がない預金はどうなるのでしょうか?
- 相続財産になる前に、不動産の所有権を放棄できるのか
-
月別
- 2025年12月 (2)
- 2025年10月 (1)
- 2025年8月 (1)
- 2025年5月 (1)
- 2024年4月 (1)
- 2022年9月 (1)
- 2021年9月 (2)
- 2020年9月 (1)
- 2020年6月 (1)
- 2020年3月 (1)
- 2020年1月 (1)
- 2019年12月 (1)
- 2019年7月 (2)
- 2019年5月 (2)
- 2018年12月 (1)
- 2018年11月 (1)
- 2018年9月 (1)
- 2018年8月 (1)
- 2018年7月 (1)
- 2018年6月 (1)
- 2018年5月 (2)
- 2018年4月 (1)
- 2018年1月 (1)
- 2017年10月 (1)
- 2017年8月 (1)
- 2017年7月 (2)
- 2016年9月 (3)
- 2016年5月 (1)
- 2016年3月 (1)
- 2016年2月 (1)
- 2016年1月 (1)
- 2015年10月 (1)
- 2015年9月 (1)
- 2015年7月 (1)