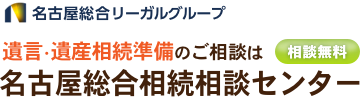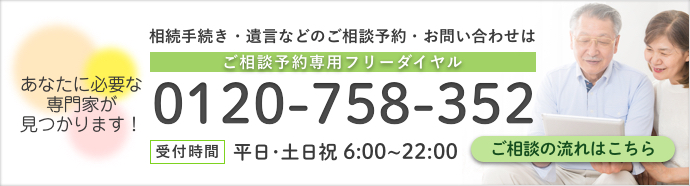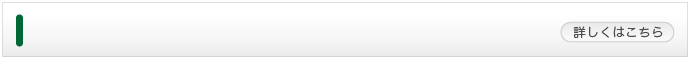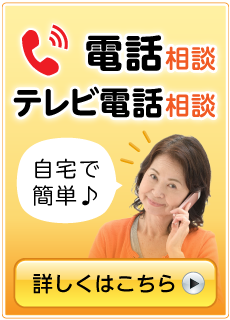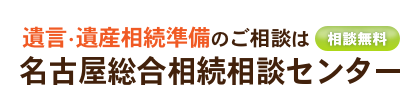ご夫婦とお子様たちのご家族のための生前対策
公開日:2020年7月17日 / 更新日:2024年6月27日
1. はじめに

相続とは、亡くなった方の財産(遺産)を相続人に承継させる制度です。
一見すると単純な制度である相続ですが、実際には相続トラブルは後を絶ちません。
その原因は様々でしょうが、こうした相続トラブルは生前対策を怠っていたことが原因になることもあります。
そこで、今回は1組の夫婦とその子が相続人になる基本的ケースを前提とした相続に関する生前対策について解説します。
2. 生前贈与・遺言により特定の遺産を特定の者に承継させる!
民法は相続のルールを定めてはいますが、もちろん個別の家族の事情を踏まえて具体的ルールを決めているわけではありません。
そのため、生前より居住している自宅を相続により子と共有することになり、売却を希望する子と居住を継続したい親との対立が起こるなどの問題が生じるのです。
こうしたトラブルを回避するには、相続人が自分の遺産の承継先を自分自身により決めることができればよいのです。
これを実現する制度が生前贈与と遺言です。
どちらも、自分の財産を自分の望む者に承継させる行為です。
たとえば、妻には自宅に住み続けて欲しいのであれば、自宅を妻に生前贈与あるいは遺言により単独相続させればよいのです。
これにより、無用な親子の諍いを回避できます。
特に、平成30年の改正相続法では、長期(20年以上)婚姻中の夫婦間における生前贈与・遺贈の対象になった居住用不動産は後の相続において遺産となるべき財産として考慮されないことになり、 配偶者の居住権の保護は手厚くなりました。
なお、法律は生前贈与や遺言でも侵害することを許さない相続人に保証された相続分を認めており、これを遺留分といいます。
もし、遺留分を侵害するような生前贈与や遺言の作成された場合には、
後に遺留分減殺請求という侵害の回復のための金銭的請求のなされる可能性がありますから、その点は注意するようにしましょう。
3. 相続税の負担によるトラブルを回避する方策
相続により遺産を承継した場合には、その相続財産の評価額に応じて相続税を課せられます。
そして、税金は金銭により支払することになりますから、不動産のような金銭以外の相続財産を承継した場合には、税金の支払に窮してしまうことがあります。
特に、その不動産に居住する必要があるようなときには、簡単に売却して税金を支払うための金銭を得るということもできません。
このような相続税の負担によるトラブルを回避する方策はいくつかあります。
まず、生命保険に加入して、万が一のときに備え、現金を手元に入るようにしておくのです。そうすれば、税金の支払に窮することはないでしょう。
また、相続財産の評価額を事前に下げておくことにより、相続税の額を抑える方法があります。
たとえば、他人に賃貸している不動産の価値は、そうでない場合と比較して安くなります。
もし、特に使う予定のない不動産が遺産になりそうであれば、生前より他人に賃貸しておくと後の相続の際の節税になります。
そのほか、相続税の負担を軽減する方策はいくつかありますから、詳しく知りたい方は最寄の税理士などに相談してみてください。
4. まとめ
相続は亡くなった人の財産を相続人に承継させる単純な制度ですが、トラブルの生じやすい制度です。
その原因の1つは法律に従った相続は実際のニーズに反することがあること、他の1つは相続税の負担によるものです。
このような2つの問題を解決する方策としては、生前贈与や遺贈により実際のニーズに応じた相続を実現させることと、相続税の軽減と税金支払のための現金の確保のための対策が挙げられます。
死は突然やってくることがありますし、生前対策には専門的知識が必要となることが多いです。
また、色々な生前対策には、それぞれメリットもあれば、デメリットもあります。
したがって、相続の生前対策は、なるべく早めに検討すべきですが、その場合でも、焦ることなく、一度は税理士や弁護士などの専門家に相談してみるようにしましょう。