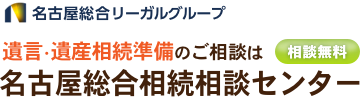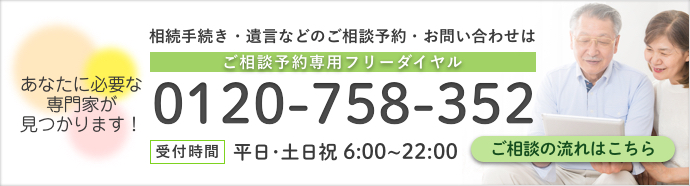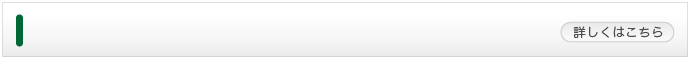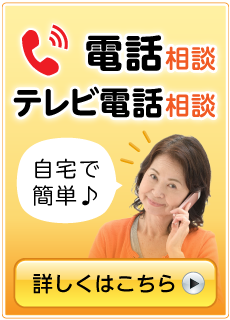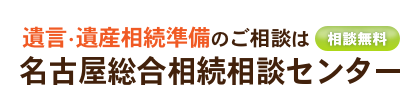生前対策として贈与を考えています。具体的な方法を教えてください

贈与とは
贈与とは、「当事者の一方が事故の財産を無償で相手方に与える意思表示をし、相手方がこれを受諾することによって成立する契約」をいいます。
贈与の方法には以下のものがあります。
- 1 暦年贈与
- 2 相続時精算課税
- 3 都度贈与
- 4 贈与税の非課税制度
1.暦年贈与
暦年贈与とは、1年間に贈与を受けた財産の価額が基礎控除額(110万円)以下の場合、贈与税が非課税となる暦年課税制度を利用した贈与方法です。贈与した人が死亡した場合、死亡前3年分(令和9年以降、順次年数が1年ずつ増加し、令和13年以降は7年となります。)の贈与財産は相続財産に加算され、相続税額が計算されます。
2.相続時精算課税
原則として60歳以上の直系尊属(父・母・祖父・祖母など)から18歳以上の直系卑属(子・孫など)である推定相続人に、暦年単位による暦年贈与に変えて適用を受ける贈与です。適用を受ける受贈者(子・孫)が「相続時精算課税選択届出書」を税務署に提出することにより、選択できます。また、選択の取り消しはできません。
令和6年1月1日以降に贈与により取得する財産については、暦年贈与の基礎控除額とは別に、受贈者1人につき、贈与税の課税価格から110万円(基礎控除額)が控除できます。また、この基礎控除額を超えた金額が贈与した人の相続の際に相続財産として加算されます。
贈与時には基礎控除額(110万円)及び特別控除額(累計で2,500万円)を超える部分について一律20%の税率による贈与がかかります。この時支払った贈与税額は相続税額から控除されます。
【贈与税額の計算方法】
(A―110万円―B)×20%
A:特定贈与者ごとの贈与財産の価額
B:特定贈与者ごとの特別控除額2,500万円
(前年以前に控除した金額があるときは、その残額)
3.都度贈与
扶養義務者が子供などのためにその都度負担する金額をいい、贈与税の非課税としされます。
- ・生 活 費:通常の日常せいかつを営むのに必要な費用
- ・教 育 費:子や孫の教育上通常必要と認められる学資、教材費、文具費等の費用
- ・結婚費用:婚姻に当たって、親から婚姻後の生活を営むために家具や家電製品等の通常の日常生活を営むのに必要な家財や購入のため金銭の贈与を受け場合
- ・出産費用:出産にあったって検査・検、分娩・入院に要する費用を親が負担した場合
4.住宅取得等資金の贈与
令和8年12月31日までの間に、特定受贈者(※)が直系尊属(祖父・祖母・父・母など)から以下の要件を満たす贈与を受けた場合、に満30歳未満の人がその直系尊属(祖父・祖母・父・母など)から教育資金に当のための金銭の贈与を受け、翌年の3月15日までに一定の新築等をすために、金融機関等と金融資金管理契約(信託契約)を結んだ場合には、1,500万円まで贈与税が非課税となります。
この制度は暦年贈与の基層控除額と併用できます。つまり住宅取得費課税額+110万円までが非課税で贈与できます。
また、贈与税で非課税とされた金額は相続財産からも除外されます。
5.教育資金の一括贈与
令和8年3月31日までの間に、満30歳未満の人がその直系尊属(祖父・祖母・父・母など)から教育資金に当たるために、金融機関等と金融資金管理契約(信託契約)を結んだ場合には、1,500万円まで贈与税が非課税となります。
契約期間中に贈与した人が死亡した場合は、相続時点の財産は相続財産に加算されます。しかし、贈与を受けた人が23歳未満の場合には、原則として相続財産には加算されません。
6.結婚・子育資金贈与
令和7年3月31日までの間に、18歳以上50歳未満の人がその直系尊属(祖父・祖母・父・母など)から結婚・子育て資金に当たるために、金融機関等と金融資金管理契約(信託契約)をした場合には、1,000万円まで贈与税が非課税となります。
契約期間中に贈与した人が死亡した場合は、相続時点の財産は相続財産に加算されます。
7.配偶者贈与の特例(おしどり贈与)
贈与をした日において婚姻期間が20年以上の配偶者から、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与を受けた場合、贈与税の課税価格から2,000万円が控除されます。
また、この贈与により取得した財産は相続財産から贈与をした配偶者がなくなった際、贈与をした人の相続財産には含まれません。そのため基礎控除額+2,000万円の財産の方は、生前にこの規定を適用して基礎控除額以下にすることができます。
【計算の仕方】
(1-②―110万円)×税率=贈与税額
1 その年分に贈与を受けた金額
2 贈与税の配偶者控除
次のいずれか少ない金額
イ.2,000万円
ロ.居住用不動産の価格+居住用不動産に充てた金銭
手続き
贈与を受けた年の翌年の2月1日~3月15日に、一定の書類と添付した贈与税の申告書を、財産をもらった人(受贈者)の住所を管轄する税務署に提出する必要があります。
期限を過ぎてしまうと適用できなくなる規定もありますので、事前に税理士に相談するようにしましょう。
-
最新の記事
- 熟年離婚後、元配偶者への遺言はどうなる?
- 被相続人の借金を返済してしまったが、相続放棄できる?医療費は?
- 【生前贈与の選び方】暦年贈与と相続時精算課税の違い
- 生前対策として贈与を考えています。具体的な方法を教えてください
- 高齢者の身元保証サービスとは?
- 次世代経営者へのバトンタッチ
~自社株(非上場株式)等の相続税・贈与税の納税猶予の特例~ - 高齢者の生活と資産を守るための「家族信託」の活用事例
- 認知症の人の所有住宅 221万戸
- 終活と遺言
- 生命保険金の非課税枠
- 生前贈与~子や孫へ財産を引き継がせる方法
- 遺言信託とその公示
- 遺留分制度の改正により、遺留分及び遺留分侵害額の算定方法が明文化
- 配偶者居住権を活用した節税メリットとリスク
- おしどり夫婦贈与(贈与税の配偶者控除)
- 住宅取得資金等の非課税の特例
- 秘密証書遺言書
- 配偶者なき後問題
- 10年以上取引がない預金はどうなるのでしょうか?
- 相続財産になる前に、不動産の所有権を放棄できるのか
-
月別
- 2025年12月 (2)
- 2025年10月 (1)
- 2025年8月 (1)
- 2025年5月 (1)
- 2024年4月 (1)
- 2022年9月 (1)
- 2021年9月 (2)
- 2020年9月 (1)
- 2020年6月 (1)
- 2020年3月 (1)
- 2020年1月 (1)
- 2019年12月 (1)
- 2019年7月 (2)
- 2019年5月 (2)
- 2018年12月 (1)
- 2018年11月 (1)
- 2018年9月 (1)
- 2018年8月 (1)
- 2018年7月 (1)
- 2018年6月 (1)
- 2018年5月 (2)
- 2018年4月 (1)
- 2018年1月 (1)
- 2017年10月 (1)
- 2017年8月 (1)
- 2017年7月 (2)
- 2016年9月 (3)
- 2016年5月 (1)
- 2016年3月 (1)
- 2016年2月 (1)
- 2016年1月 (1)
- 2015年10月 (1)
- 2015年9月 (1)
- 2015年7月 (1)