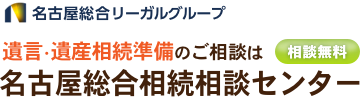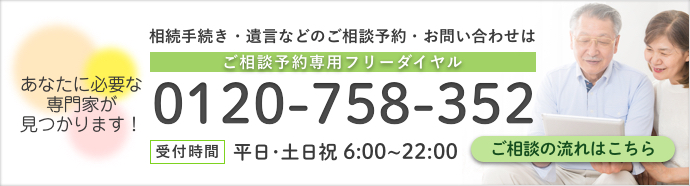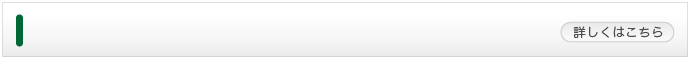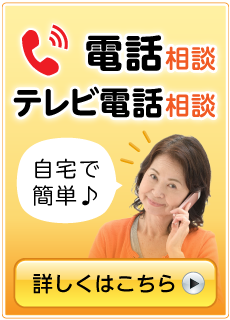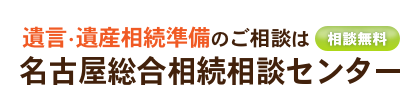高齢者の身元保証サービスとは?
弁護士 杉浦恵一

高齢者の身元保証問題
令和7年1月8日の日本経済新聞の記事で、高齢者の身元保証に関して、トラブルが急増しているという報道がありました。その内容としては、高齢者の身元保証や死後の事務手続を家族に代わって担うサービスを巡って、消費生活センターへの相談が急増しているということです。
国民生活センターに寄せられた相談件数としては、ここ10年ほどは年間100件から200件程度だったものが、2023年には300件を超えているということです。
このような問題の背景には、少子高齢化により身近に頼ることができる親族がおらず、第三者・組織・団体に頼らざるを得ないという問題があるようです。
「身元保証」とは
そもそも「身元保証」とはどのようなことを指すのでしょうか。法律上では「身元保証に関する法律」という法令がありますが、これは雇用の際に身元等を保証することに関して規制をする法律ですので、高齢者の問題を規制するものではありません。
法律上、高齢者の「身元保証」を定義したり、規制、管轄する法令がありませんので(「社会福祉法」など施設を規制する法令を除き)、高齢者の「身元保証」というのは、各団体・各サービス提供者によって内容が異なっているのが現状です。
一般的に高齢者の「身元保証」サービスとして提供されているのは、①病院に入院する際や介護施設に入所する際に身元引受人になったり、緊急連絡先、保証人になったりすること、②高齢者の財産管理、収支の管理、支払いのサポート等をすること、③高齢者の死亡後の火葬、納骨、遺品処分などの死後事務委任、といったことが想定されているようです。
「成年後見」との違い
主に高齢者に代わって財産管理等をすることとして、民法上の「成年後見」等の制度はありますが、成年後見の場合には、本人が「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある」こと(民法7条)が必要になってきますので、物事を理解・判断する能力が本人に備わっている間は、このような成年後見は利用することができません。また、成年後見では、現状では全面的に成年被後見人が財産管理等をすることになっていますので、一部の事柄だけを行うということができません。
そのような状況であるため、民間の高齢者身元保証等のサービスに需要が生じていると考えられます。
身元保証サービスによるトラブル
そのような中、高齢者の「身元保証」サービスによるトラブルが急増しているという記事がありましたが、前記の記事で挙げられている事例としては、想定していたよりも利用料がかかる(高額)であったり、契約がきちんと履行されない、解約しても全額が返金されない、といったようなトラブルが多いようです。
また、法的な紛争としては、利用者とサービス事業者との間で利用者の財産をサービス事業者に贈与、死因贈与、遺贈といったことをして、利用者の相続人との間で相続に関するトラブルになることもあるようです。
これまではこのような高齢者の身元保証や財産管理は、配偶者、子供や兄弟姉妹、親戚などの親族が行ってきたのではないかと思われます。
しかし、少子高齢化や非婚化により、親族が少なくなり、またはいなくなった結果、このようなサービスに頼らざるを得なくなっていると考えられます。
身元保証サービスの今後
このような身元保証等のサービスに関して、現在ある問題点としては、このようなサービス事業を包括的に管轄、規制する法令や官庁がなく、個別の問題は民法などの一般法に頼って解釈等をせざるを得ない、ということではないでしょうか。
民法や消費者関連の法令では、個別の行為について規制し、解決することができるかもしれませんが、事業者そのものについて何らかの規制をすることができず、最低限の信頼ができる業者なのか(例えば何かあった際に資力があるのか否か、利用者とサービス提供者の人数比が適正なのか等)が分からず、安心して契約できるかどうかが分からないことが問題点として挙げられます。
今後、このような高齢者の身元保証等のサービスの需要が増えていくのではないかと思われますので、何らかの規制や基準が必要になってくるのではないかと考えられます。
-
最新の記事
- 熟年離婚後、元配偶者への遺言はどうなる?
- 被相続人の借金を返済してしまったが、相続放棄できる?医療費は?
- 【生前贈与の選び方】暦年贈与と相続時精算課税の違い
- 生前対策として贈与を考えています。具体的な方法を教えてください
- 高齢者の身元保証サービスとは?
- 次世代経営者へのバトンタッチ
~自社株(非上場株式)等の相続税・贈与税の納税猶予の特例~ - 高齢者の生活と資産を守るための「家族信託」の活用事例
- 認知症の人の所有住宅 221万戸
- 終活と遺言
- 生命保険金の非課税枠
- 生前贈与~子や孫へ財産を引き継がせる方法
- 遺言信託とその公示
- 遺留分制度の改正により、遺留分及び遺留分侵害額の算定方法が明文化
- 配偶者居住権を活用した節税メリットとリスク
- おしどり夫婦贈与(贈与税の配偶者控除)
- 住宅取得資金等の非課税の特例
- 秘密証書遺言書
- 配偶者なき後問題
- 10年以上取引がない預金はどうなるのでしょうか?
- 相続財産になる前に、不動産の所有権を放棄できるのか
-
月別
- 2025年12月 (2)
- 2025年10月 (1)
- 2025年8月 (1)
- 2025年5月 (1)
- 2024年4月 (1)
- 2022年9月 (1)
- 2021年9月 (2)
- 2020年9月 (1)
- 2020年6月 (1)
- 2020年3月 (1)
- 2020年1月 (1)
- 2019年12月 (1)
- 2019年7月 (2)
- 2019年5月 (2)
- 2018年12月 (1)
- 2018年11月 (1)
- 2018年9月 (1)
- 2018年8月 (1)
- 2018年7月 (1)
- 2018年6月 (1)
- 2018年5月 (2)
- 2018年4月 (1)
- 2018年1月 (1)
- 2017年10月 (1)
- 2017年8月 (1)
- 2017年7月 (2)
- 2016年9月 (3)
- 2016年5月 (1)
- 2016年3月 (1)
- 2016年2月 (1)
- 2016年1月 (1)
- 2015年10月 (1)
- 2015年9月 (1)
- 2015年7月 (1)