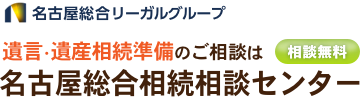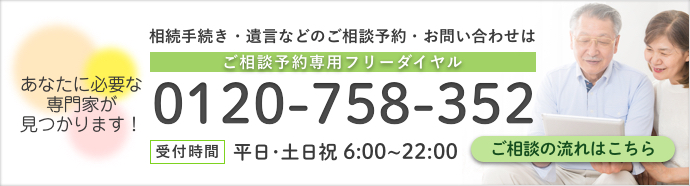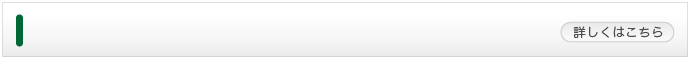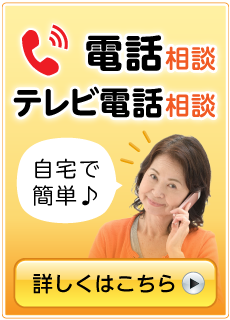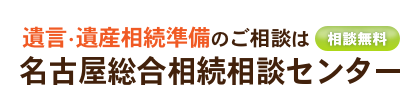遺言の執行
公開日:2016年8月3日 / 更新日:2019年4月5日
(1)遺言の検認
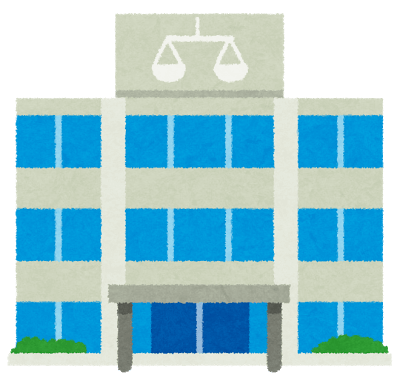
自筆の遺言書を発見した場合には、まずは適切に保管し、その遺言書を家庭裁判所に持参して「検認」の手続きを行う必要があります。勝手に開封してはいけません。
「検認」とは、遺言書の状態・形状・内容を確認する手続きです。家庭裁判所で、相続人の立会いの下、遺言書が開封され検認されます。(ただし、検認手続きは、遺言の有効性を保証するための手続きではありません。)
※公正証書遺言の場合は検認手続きは不要です。
(2)遺言の執行

遺言書の内容は、誰かがそれを行動に移すことで初めて実現されます。
遺言の執行は、相続人自身で行うことができますが、相続人が複数いて、相続財産が多数ある場合には、それぞれの財産の処分ごとに相続人全員が関与(書類への実印での押印等)することは非常に面倒です。また、行方不明の相続人がいる場合、不在者財産管理人を家裁で選任してもらわなければ手続きを進めることができません。
⇒遺言執行者という制度が法律で設けられています。遺言執行者は相続人の代理人とみなされ、遺言の執行に必要な一切の行為をする権利・義務を有しています。遺言者は、遺言の中で遺言執行者を指定することができます。信頼できる人を遺言執行者に指定しておくとよいでしょう。
- 遺言の種類
- 遺言書の書き方
- 遺言書の保管方法
- 遺言の執行
- 遺言書作成例
- 遺言書作成例1:妻に全財産を残したい!~すべての財産を妻に相続させる遺言書~
- 遺言書作成例2:妻と子供に特定の財産を残したい!~特定の財産を妻と子供に相続させる遺言書~
- 遺言書作成例3:妻と子供に法定相続分と異なる割合で財産を残したい!~相続分を指定する遺言書~
- 遺言書作成例4:内縁の妻に全財産を残したい!~すべての財産を相続人でない人に遺贈する遺言書~
- 遺言書作成例5:甥と姪に特定の財産を残したい!~特定の財産を相続人でない人に遺贈する遺言書~
- 遺言書作成例6:子供を認知し財産を残したい!~遺言執行者を指定して遺言による認知をする場合~
- 遺言書作成例7:遺言執行者を指定しておきたい!~弁護士法人を遺言執行者に指定する遺言書~
- 遺言書作成例8:祭祀承継者を指定しておきたい!~長男を祭祀承継者に指定する遺言書~
- 遺言書作成例9:相続人が遺言者より先に亡くなってしまうかもしれない!~予備的遺言を入れる場合~
- 遺言書作成例10:妻の老後が心配で、誰かに妻の面倒をみてもらいたい!~甥に不動産を遺贈する代わりに、妻の生存中は生活費を支払ってもらう負担付遺贈の遺言書~
- 遺言書作成例11:長女に結婚資金の贈与をしているが、相続分の算定の際に入れたくない!~特別受益の持戻し免除をする場合~
- 遺言書作成例12:財産を与えたくない相続人がいる!~相続人を廃除する遺言書~
- 遺言書作成例13:昔作った遺言書をなかったことにしたい!~以前の遺言を撤回する場合~
- 遺言書作成例14:財産を寄付したい!~財産を日本赤十字社に寄付する場合~
- 遺言書作成例15:遺言の内容について、自分の気持ちを残したい!~付言を入れる場合~