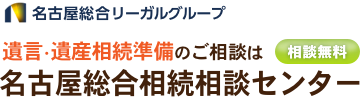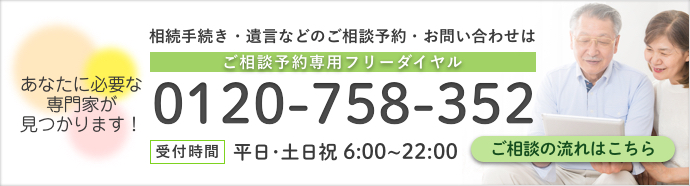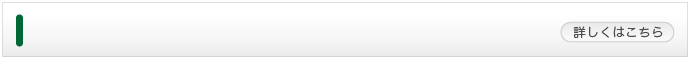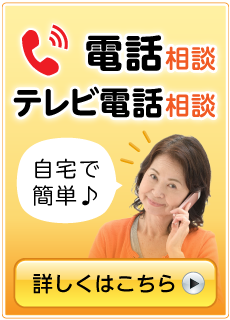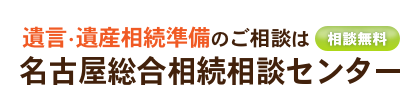認知症の相続人がいる場合
公開日:2020年6月10日 / 更新日:2022年9月27日
始めに
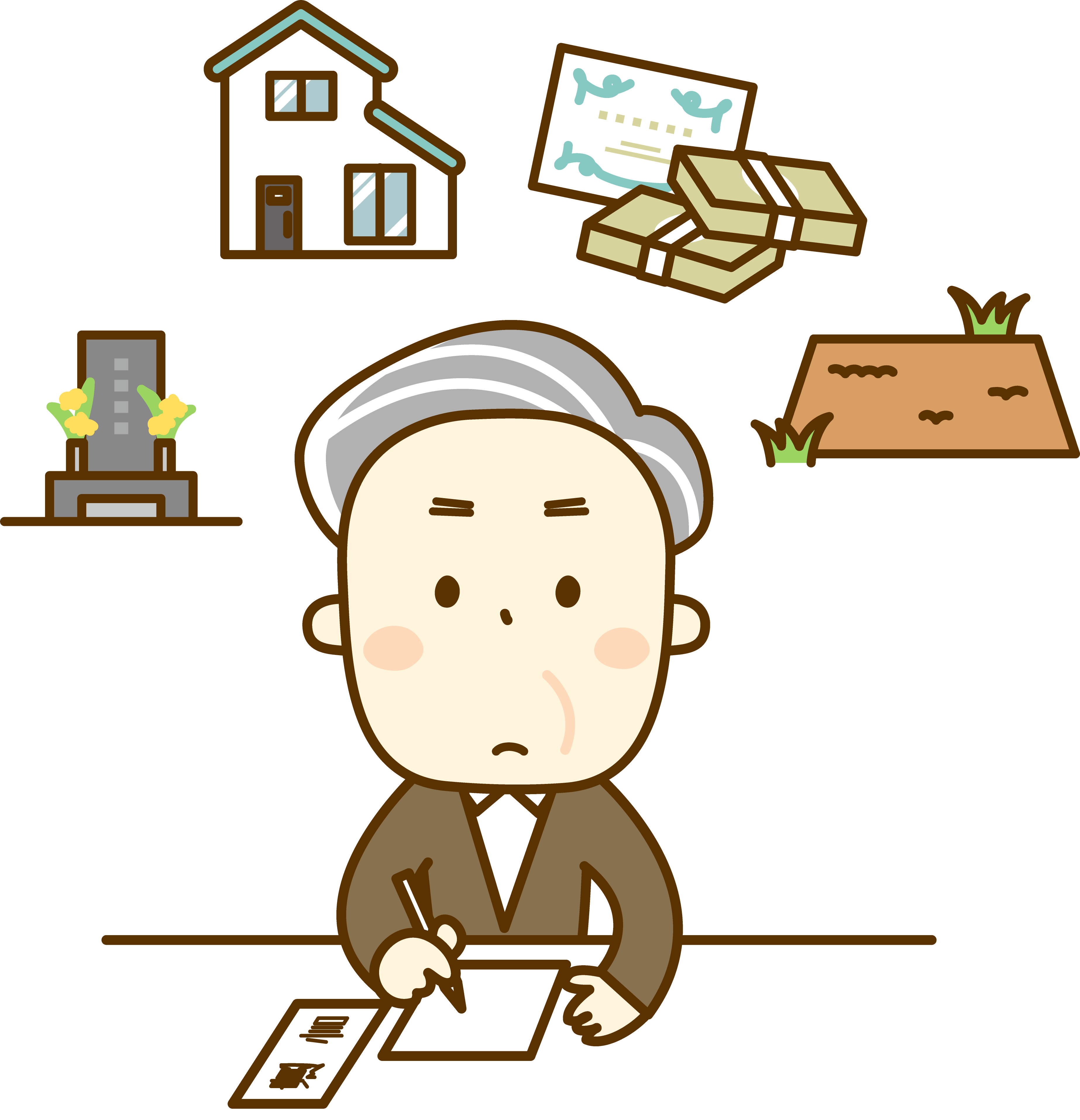
内閣府の「令和元年版高齢社会白書」によると、2018年時点で、65歳以上の人口は3558万人となり、総人口に占める割合(高齢化率)は28.1%となっています。
今後の推計値では、2025年には高齢化率が30.0%に、その後も増加傾向が続くとされています。
このような状況で、相続においても高齢化が問題となるケースがでてきます。
法定相続について
被相続人だけでなく、相続人も高齢なことが多く、例えば、高齢の御主人が亡くなり、相続人である奥様も高齢で認知症を患っていることもあります。
相続手続きにおいて遺産分割協議が必要となりますが、相続人の中に認知症の方がいると遺産分割協議ができなくなります。
相続手続きの方法として、遺産分割でなくとも法定相続により法定相続分の割合で取得することもできますが、法定相続には以下のようなデメリットがあります。
① 「相続税対策として有利な選択ができない」
相続税申告に小規模宅地の特例を適用するなど相続税を下げるための有利な方法をとるためには、遺産分割協議をする必要があります。
また、御主人の相続(一次相続)の後に将来やってくる奥様の相続(二次相続)も考慮した遺産分割をした方が相続税がトータルで有利になることもあり、その為には遺産分割協議をする必要があります。
②「不動産が共有名義になってしまう」
不動産の名義が複数人での共有になると権利関係が複雑になり、のちのちのトラブルにもなるので、できるだけ避けた方が望ましいです。
相続人のうち特定の方の単独名義にするためには、遺産分割協議が必要です。
成年後見制度の利用
相続人に認知症の方がいる場合に遺産分割協議を行うためには、成年後見制度を利用することになります。
家庭裁判所へ申立てをおこない、成年後見人を選任してもらいます。
その成年後見人がご本人に代わり、他の相続人と遺産分割協議を行います。
なお、成年後見人に家族が選任された場合、たとえば、父の死亡による相続手続きにつき、母が認知症であるため母の成年後見人に長男が選任された場合、長男は自らが父の相続人でもあるため、利益相反関係となり母の成年後見人として遺産分割協議をすることが出来ません。
このような場合には、後見監督人が選任されていればその者が、後見監督人がいない場合は、別途、家庭裁判所で特別代理人選任の手続きとり、その特別代理人が母の代わりに遺産分割協議をすることになります。
成年後見制度を利用することで、遺産分割協議ができますが、成年後見制度にはデメリットもあるので、その点も十分考慮したうえで利用するかどうか決めることが大事です。
①「途中でやめられない」
成年後見制度を利用するきっかけとしては、上記のような遺産分割が必要となって、というケースが多いですが、遺産分割が終わったら成年後見も終了させるということができません。
一旦成年後見をスタートさせると、本人の判断能力が回復するか亡くなるまで続くことになります。
成年後見制度は、ご本人の財産を守る制度になっているので、家族が成年後見人になった場合、定期的に財産管理の報告書を家庭裁判所へ提出しなければいけません。
また財産管理・処分についても融通がいかないケースもでてきます。
②「専門家が後見人となることもある」
成年後見人選任の申立てに際し、その候補者として家族の方を指定しても、実際に誰を選任するかは家庭裁判所の判断となり、事案によっては、第三者の専門家が選任されることもあります。
専門家が後見人となった場合、後見人報酬が発生し、財産や管理ないようにもよりますが月額3~5万円の報酬をご本人の財産から負担していくこととなります。
対策
推定相続人のなかに、認知症や精神障害のかたがいる場合には、ご自身の亡き後、残された家族が遺産分割をする必要がないように対策をしておけば、成年後見制度の利用を避けることができます。
それは、遺言です。
遺言により、不動産や預貯金など財産の相続先を指定しておけば、その遺言にもとづき、残された家族は相続手続きをすることができ、遺産分割する手間がなくなります。
最後に
ご自身の亡き後の心配がある場合は、お早めに弁護士など専門家に相談いただき、対策をとることをお勧めいたします。